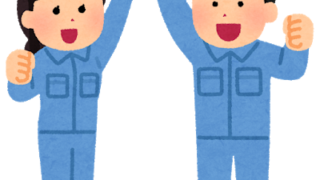 工事日報
工事日報 施工の神様の記事は面白いからおススメ
みなさん施工の神様ってサイト知っていますか?このサイトの記事がとても面白いので紹介します。建設業の情報を上げている結構有名なサイトで、サイト名からして施工の神様ってつけるぐらいですから、建設業界の裏話なんかもたまに書かれています。筆者の多く...
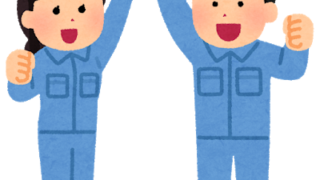 工事日報
工事日報  初めての施工管理
初めての施工管理 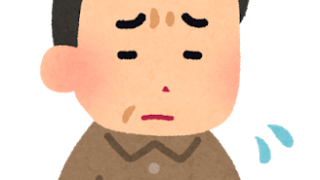 建設業
建設業  消防団
消防団  建設業
建設業  建設業
建設業  雑記
雑記  消防団
消防団  建設業
建設業  消防団
消防団  施工管理技士試験
施工管理技士試験